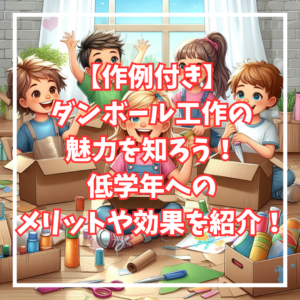工作のワークショップを大成功させる基本的な3つの流れと秘訣
「工作は、指先の器用さ向上や知育など、さまざまな良い効果が期待されている」というのはご存知の方も多いと思います。
一方で、どうすればよりうまく、体系立てて子どもたちに体験してもらえるのか、という点で悩まれている方も多いと思います。
毎日の授業や、イベント的に行う時、抑えておきたいポイントや、どんなことをすればより子どもたちが楽しく取り組めるかといった点を、この記事で紹介していきたいと思います。

ワークショップとは
まず最初に、ワークショップとはどのようなものかをご説明します。
ワークショップは、参加者が手を使って創造的な活動に取り組む場です。
ここで言う参加者は「子ども達」ですね。
工作はその中の一つの形態であり、子ども達が自分の手で物を作り、アイデアを具現化する機会を提供します。
ここまで読むと、「そのまんまだな」と思われるかもしれませんが、「ワークショップ」と「普段の工作」を分ける最も大事なものが
【気づき】
です。
・どうやってアイデアを浮かばせるか?
・それをどうやって具体化させるか?
・その中で【気づき】をどうやって得るか?
・得た気づきをどうやって定着してもらいやすくするか?
この【気づき】が生まれる事がワークショップの最大の魅力であり、目的です。
「工作」にするメリット
ワークショップは、企業研修などでも取り入れられており、ワークショップで得た【気づき】を、参加者へ学びとして定着してもらうために、【体験】という方法を用いている事が多いです。
「百聞は一見に如かず」という言葉がありますが、「聞くより、実際にみてみてみよう!」という意味ですよね。
あれには、実は続きがあります。
「百見は一考に如かず」「百考は一行に如かず」「百行は一果に如かず」と続きます。(さらに、2つ続きますが、それはまた別の機会に!)
(参考:「百聞は一見に如かず」には続きがある。”見て理解” のその先にあるたいせつなこと。)
「見るだけではなく、考えてみよう」
「考えるだけでなく、やってみよう」
「やってみるだけではなく、成果を出してみよう」
という事です。
つまり、考えたり、やってみたり、成果を出してみたり、という事が子ども達にも直観的にわかりやすいのが「工作」なんです。
具体的な流れ
ワークショップ的に工作をするメリットを見ていただけたと思いますので、それを具体的な流れで見ていきましょう!
導入
まずはワークショップの導入として、参加者に工作の目的やテーマを説明します。
例えば
【一度は住んでみたい!みんなの憧れの家を作りましょう!】
【節分の季節がやってきました。豆まきを楽しめる鬼のお面を作りましょう!】
【こんなんあったらいいな。魔法の家電作り】
などです。
テーマや目的は、その時々で「伝えたい事」を盛り込んでおきましょう。
ここで大事なのは、参加者に「その気」になってもらわないといけません。
その為に大切にしてるのは、【これから使う素材や道具を知ってもらうこと】です。
知ってもらうために、触ってもらったり、使い方を聞いて実際にやってもらうことです。
ハサミやカッターを使う場合は、必ずその危険性を伝えた上で、体験として使ってもらうことが大事です。
また、関連する資料を見せるのも良いでしょう。
冒頭の【憧れの家】がテーマなら、その関連する絵本や映像を見てもらうのもいいでしょう。
【鬼のお面】なら、鬼が出てくるような絵本や実際のお面を見せるのもいいでしょう。
そうやって、「これからやる事へのワクワク感」を高める事で「その気」になってもらい、「伝えたい事」がより伝わる土壌を作る事ができます。
時間が許すなら、全体の時間の1/5、1/4くらいを割いてしっかり伝えましょう。
実施
次に、実際に工作を行います。
「その気」になった子ども達は、すぐ手を付ける子もいますし、「どうしよう、、、」と悩む子もさまざまです。
ここで大事なのが、無理に作らせようとしないです。
ワークショップの目的は何でしたか?
「作る事」ではないですよね。
そうです。
「気付くこと」
です。
もちろん、作った方が楽しいですし、みんなと後から見せあいっこができますし、何より「一人だけ無い」というのも寂しいものです。
そんな時に、こんな事をやってみてください。
「大丈夫よ。今作れなくても、思いつかなくても全然いいよ」と認めてあげた上で
・「先生と一緒に作ろうか!」とか「先生が作るの手伝ってみて」と、誘ってみる。
・「他の子の作品探検に出かけてみよう!」「他の子のお手伝いをしてみようか」と、他の子の作品を意識する場面を作る。
・「好きな事教えてほしいな」「一番楽しかったこと聞いてもい?」など、本人のワクワクするエピソードを掘り出してあげる。
そうする事で、自分のしたい事に「気づく」チャンスができます。
そしてそんな「気づき」が出てきたらもう大丈夫。
「そうだったんだ!よしやってみよう!」って背中を押してあげてくださいね。
そうやって、子ども達の進み具合を見ながら、声がけをしてあげたり、危険が無いかをチェックしながら、進めていきましょう。
振り返り
工作が終わったら、子ども達と一緒に作品を振り返りましょう。
どうやって作ったのか、どんな問題があったのか、どんな気持ちで取り組んだのかなどを話し合い、考える機会を設けることで、より深い学びが得られます。
似たような作品ができても、実は細かい所で全く違う事は多いです。
まだ好きなポイントや、大変だったところも全然違います。
そうやって、「違いに気づく」事や、「工夫に気づく」事で、次の作品へのモチベーションや意欲に繋がります。
人数によって、全員分を振り返られない時は、3~4人グループを作り、その中で作品を見合いっこしてもらいましょう。
・作った本人から「頑張ったところ」「工夫したところ」の発表
・周りから「すごいと思ったところ」「自分が好きだと感じたところ」の発表
こんなテーマで全員発表できたら、最高ですね!
ダンボールでワークショップをしてみよう
ダンボールは工作に最適な素材です。
手軽に入手でき、創造力を存分に発揮することができます。
何より「大きな作品」を作る事がしやすく、協力して作ったり、大人と一緒に作れるというのが最大の魅力です。
紙や新聞紙ではできないけど、木材を使うのはハードルが高い。
そんな、「いいとこ取り」をしている素材がダンボールです。
プレイフルワークスでは、こうしたダンボールの工作のワークショップを、10年以上展開してきました。
私たちのミッションは
「作る喜びをすべての人に」
です。
作る喜びの中には「オモシロことを知れた」「自分自身が成長できた」「これを誰かにみてほしい!」「私、こんな事もできたんだ!」という発見があります。
よく、工作キットで、手軽にできる「ダンボールのおもちゃ」を作ってもらうだけでももちろんいいのですが、ダンボールを通じて、「気づき」がある事で、より特別な体験と、そして学びに繋がると信じています。
そうしたことに興味がある方は、是非お問い合わせください。
楽しく遊び、学び、想像力と好奇心を育てるワークショップを、是非あなたの町でもやってみてくださいね。